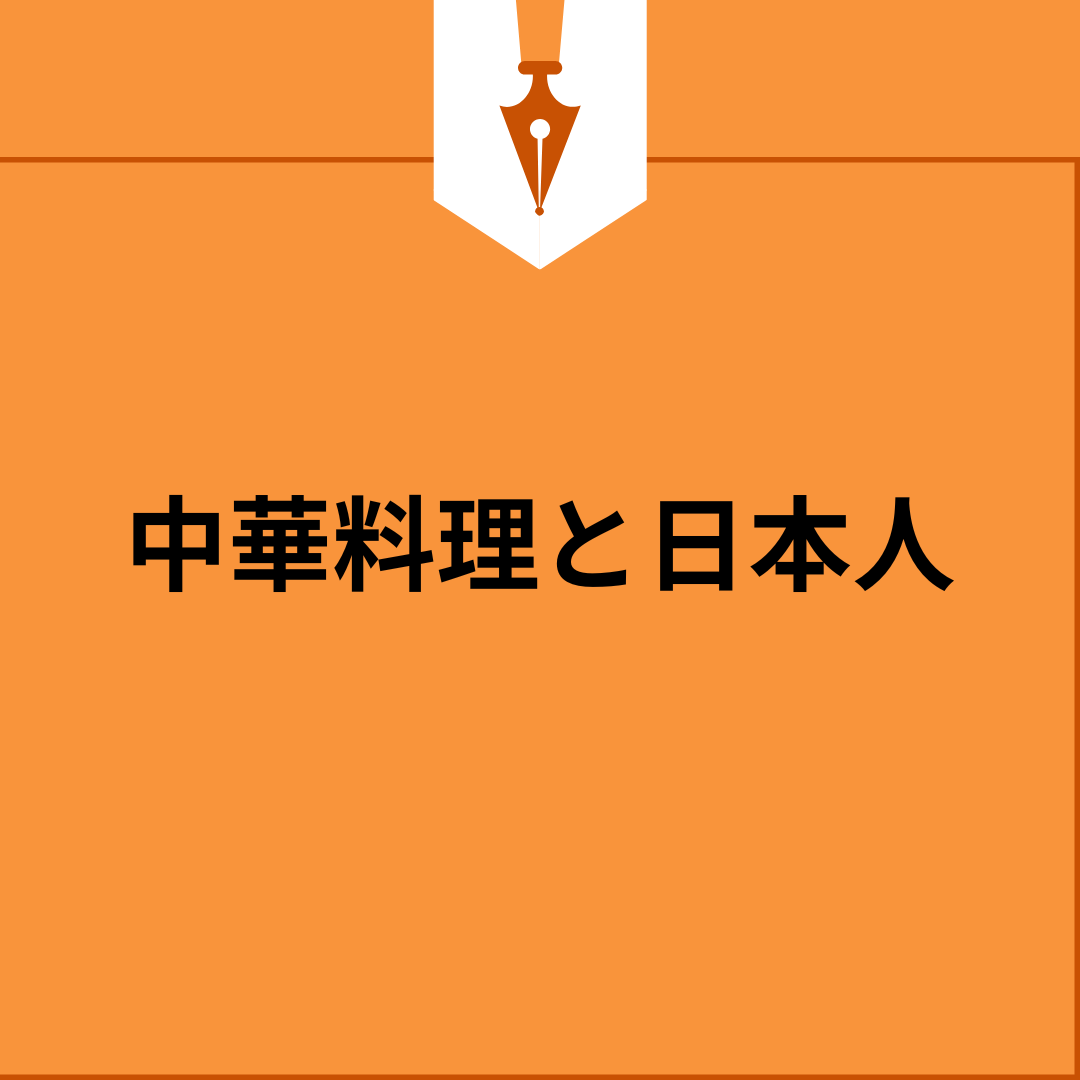帝国と帝国後の時代を生きた人々は、いったいどんな信念や意欲に的な駆り立てられて、中華料理を日本のものにしてきたのかを辿る、著者は岩間一弘、慶應義塾大学文学部教授、専門は東アジア近現代史食の文化交流史、東京大学大学院総合文化研究科博士課程修了、著書「上海大衆の誕生と変貌―近代新中間層の消費・動員・イベント」
概要
肉まん―近代的な食文化としての中華料理、1肉まんの歴史、2日本食の近代化の中の肉まん、3アジア主義と帝国主義の文化的な影響、ジンギスカン料理―満州名物から北海道遺産へ、1北京から満州・モンゴル・そして東京へー帝国の時代、2中華料理から北海道の郷土料理へ―帝国後の時代、餃子―満州の記憶とポスト帝国主義、1餃子の伝来ー近世から日中戦争、2引揚者料理としての餃子ー戦後、ウーロン茶―忘れられた台湾文化、1ウーロン茶の世界史、2日本帝国におけるウーロン茶の消費文化、3日本の国民的飲料になるウーロン茶、シュウマイ・ラーメン・四川料理ー郷土料理の創造とノスタルジア、1横浜名物になるシュウマイ、2なぜ札幌でラーメンなのか、3麻婆豆腐のノスタルジアと担々麺の郷土料理化、4中華料理の現在までの変化、世界史の中の日本中華料理、1帝国主義は料理をどう変えたのかー20世紀前半、2ノスタルジアはなぜ生まれたのか―21世紀、
感想
凱旋料理が始まり、志那料理へのノスタルジア、肉まんは肉料理の提唱から、ジンギスカン料理は満州国の名物料理から北海道の郷土料理化、餃子は引揚者により伝えた料理、ウーロン茶は台湾の特産品が国民的飲料へ、シュウマイは横浜地元実業家の努力で全国化、札幌ラーメンは関東や関西の雑誌・百貨店・食品メーカーの働きかけから、担々麺は四川料理というよりはラーメンとして定着、中国野菜は日中国交正常化からブーム、料理が文化遺産となるときを探る
まとめ
中華料理に込めた対中・対日感情、肉まん、ジンギスカン料理、餃子、ウーロン茶、シュウマイ・ラーメン・四川料理、世界史の中の日本中華料理を考察、今の中華料理に日本の帝国主義の歴史が関わっている、