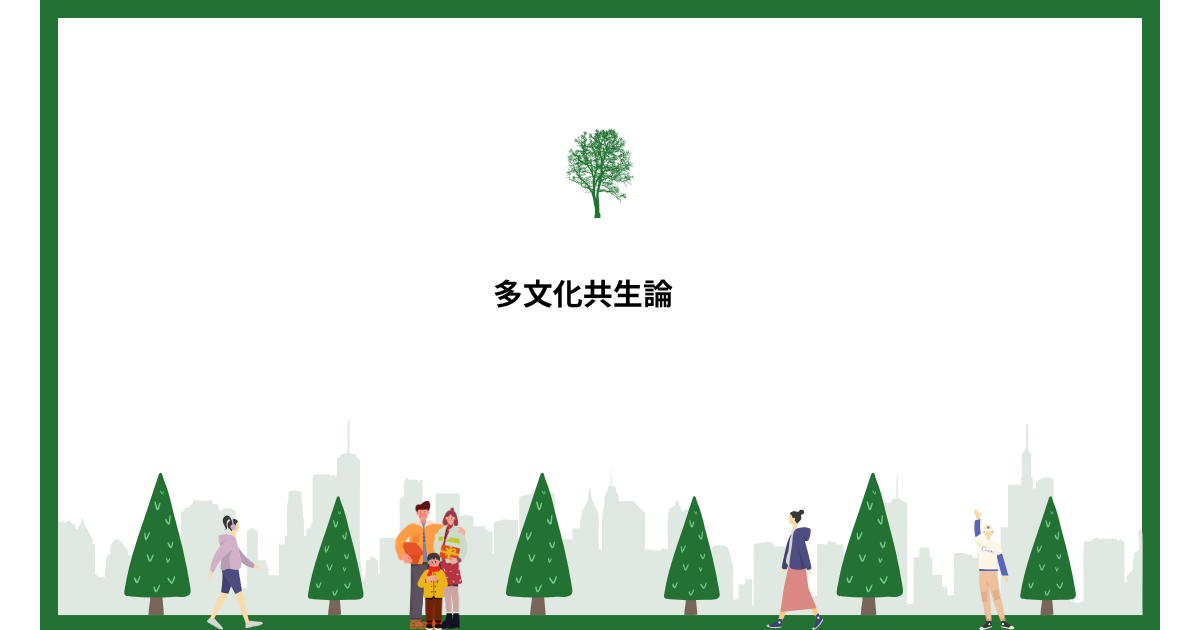多様な背景を持つ人々が相互理解し共に生きて生きていくために、どのように関わったらよいか当事者の始点で考える、編著者は加賀美富美代、東北大学大学院文学研究科博士後期課程修了、お茶の水大学名誉教授、著書「異文化葛藤と教育価値観―日本人教師と留学生の葛藤解決に向けた社会心理学研究」他
概要
多文化共生とは何か、1地域住民のコンフリクト、2コンフリクトをどのように考えるか、3外国につながる子供たちのアイデンティティと異文化受容態度、4ことばの問題の解消に向けて、5多文化共生とコミュニティ心理学、6多様性を考える、日本の外国人が抱える諸問題、1在日外国人の現況、2在日外国人の歴史的展開、3移民と難民、4地域の外国人の暮らしと国際交流、5日本社会の課題、中国帰国者の抱える問題、1中国帰国者とは、2中国残留孤児問題の解決に向けた国の取り組み、3帰国者の受け入れ体制、」4中国帰国者一世・二世・三世・4世の抱える門外と求められる求められる支援、5今後の課題とまとめ、地域社会と多文化共生、1問題の所在、子供と新大久保、3日本語学級の取り組み・実践、4)2人の子供、5日本語学校と普通学級での授業、外国につながる子供たちの困難・支援・対処行動、1外国につながる子供たちと日本の」学校、2外国につながる子供たちへのサポート、3外国につながる子供たちの困難対処、地域日本語教育とコーディネーターの重要性1地域日本語教育という概念誕生までの経緯、2地域日本語教育の展開、3地域の状況変化に応じた先駆的自治体の対応と社会状況の変化、4地域日本語教育の新たな展開、」5リーマンショックによる変化、6今後の課題、国際結婚家族で母語を身につけるバイリンガル、1家族の言語、社会の言語、2国際結婚家族の子供の言語発達3日本語、英語の同時バイリンガル、4国際結婚家族の母語と二言語のダイナミズム、国際結婚の解消、1Pの国籍は日本にあるのか、夫婦の離婚の手続き、3外国籍の母親Bの在留資格は離婚で影響を受けるのか、障害者と多文化共生、1障害学(ディスアビリティ・スタディーズ)と社会モデル、2障碍者差別と合理的配慮、3合理的配慮の起源、障害の文化モデル、5配慮の平等、性の多様性とこころの支援、1性別とは、2好きになる性別とは、3現状と歴史、4社会の取り組み」、5支援の取り組み、6マイノリティ共感という支援の視点、7今後の課題、外国人のこころの支援、1多文化精神医療の歴史、2東京都心の一クリニックを受信する外国人、3クリニックにおける外国人の精神医療、4外国人労働者と留学生について、5外国人における精神医療、6日本の難民政策と難民認定申請者のメンタルヘルス、職場と多様な在留資格の外国人就労者、1日本社会における外国人就労者の現状、2外国人就労者の受け入れ政策と課題、3職場における外国人就労者の葛藤、4葛藤を超えて、5まとめと今後の課題、大学コミュニティにおける多文化共生1多文化共生に向けた教育整備の必要性と文化的多様性の尊重、2留学生の抱える悩みはどうようなものか、3大学における異文化接触の現状と問題、4異文化交流を妨げる問題と肯定的な異文化交流のための枠組み、5共生をめざすさまざまの取り組み、6大学キャンパスにおける共生の実現に向けて、海外の日本人駐在家族と移動する子供たち、1日本人の海外駐在派遣の変遷、2日本人海外駐在員とその家族が抱える問題、3帰国した家族の抱える問題、4海外赴任者とその家族のために何ができるのか、5これからの海外赴任に向けて、韓国に移住する家族とその子供たち、1移住労働者、2結婚移民者、3移住労働者家族と国際結婚家庭の子供たち、4学校教育に見る韓国社会の対応と課題、
感想
地域住民とのコンフリクト、在日外国人問題、中国帰省者が抱える問題、子供と大久保、在日子弟と日本の学校、地域の日本語教育、国際結婚と言語と解消、障害者と合理的配慮、性の多様性と心の支援、精神科医と外国人、外国人就労者、留学生の抱える悩み、海外の駐在員とその家族、韓国移住者とその家族を取り上げ多様性を理解のためのヒントとレッスンが描かれている、
まとめ
多文化共生とは何か、日本の外国人が抱える問題、中国帰省者の抱える問題、地域社会と多文化共生、外国につながる子供たちの困難地域日本語教育とコーディネーターの重要性、国際結婚家族で母語を身に着けるバイリンガル、国際結婚の解消、障害者と多文化共生性の多様性と心の支援、外国人への心の支援、職場と多様な在留資格の外国人就労者、大学コミュニティにおける多文化共生、海外日本人駐在員家族と子供たちを考察、研究課題とキーワードを解説、