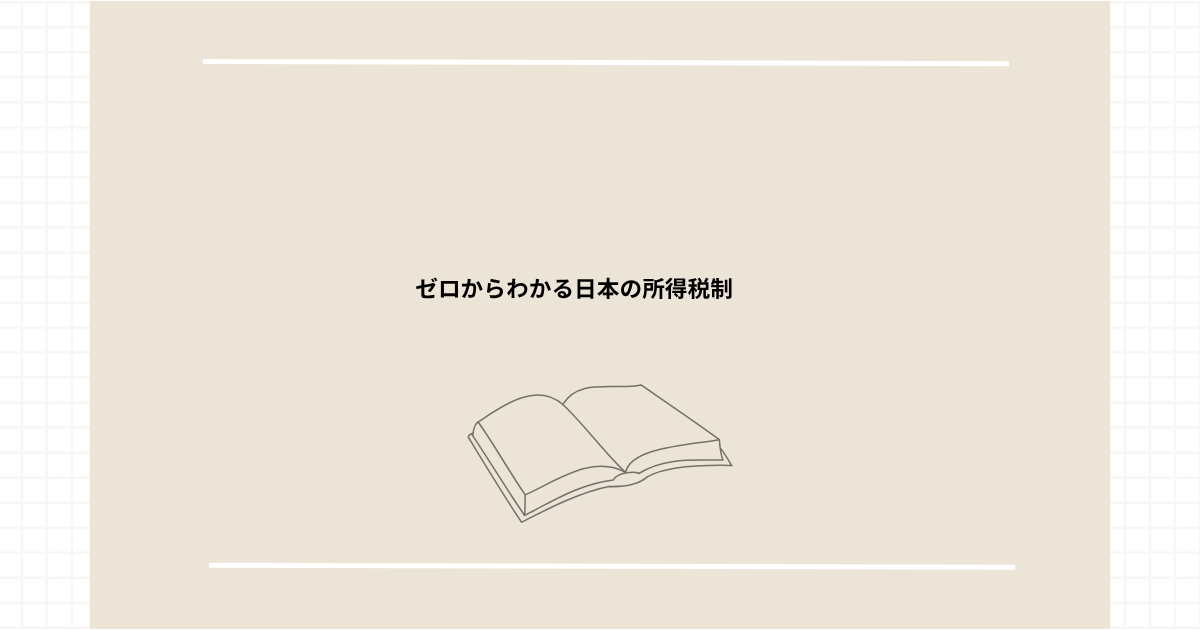税制は簡素・公平・中立であるべき、理論と理屈から税制を考える、著者は木山泰嗣、青山学院大学教授、著書「税務訴訟の法律実務」他
概要
わたしたちの税金はどのように決められるのか、税金に関心を持ちにくい給与所得者、納税の義務と納税を受ける権限税金の種類と税法、納税義務を発生させる課税要件、権力者の恣意的な所得税の課税を防ぐ租税法律主義、税制改正大綱には・国民の意見が反映されてこなかった、所得税はどのように計算されるのか、所得税の大部分を占める源泉所得税、所得税を確定させる確定申告、累進税率によって所得の再配分を担う所得税、課税される所得とは、理論所得は収入ー経費、プラスは所得、マイナスは損失、理論所得の内容、法人にも所得がある、理論所得とは・あらたな経済的価値、所得税法で定められた所得の種類は10個、所得の種類の違いと非課税、総合課税と分離課税、経費の実学控除と概算控除、理論所得からの控除と税額からの控除、所得控除の内容と存在理由、103万円の壁問題の本質、103万円の壁と生存権、基礎控除とその改定、改定された課税最低限の問題点、所得制限には妥当性があるか、税法理論に即していた国民原則の民主党、健康で文化的な最低限の生活をするための最低生活費、サラリーマンにも経費の控除がある、給与収入に応じて変わる給与所得控除額、子育て世帯にある追加の控除、サラリーマン税金控除、特定支出控除の創設、控除の上限額の導入と上限額の引き下げ、公的年金等控除額課税されない枠、基礎控除の影響力控除と非課税の違い、給与所得控除額の性質と改正、所得控除を制限する税制のトレンドは妥、当か、ど生存権と立法裁量、高所得者に基礎控除は必要ないのか、合理的に説明ができない基礎控除、生活費控除の原則の意味、配偶者控除の改正、配偶者控除の所得制限、社会保障給付の分野では撤廃され始めた所得制限、生活費控除と所得制限、大学生の親の扶養控除はどう変わった、拡大された大学生年代の扶養控除、元祖・103万円の壁、もともとあった勤労学生控除、高校生になるまで扶養控除が全くない現状、逆風にさらされ続けてきた子育て世代、少子化対策というトレンド、憲法の理念に反する税制の源流は、細かく複雑にでよいのか、平成22年改正と今後の改正、給与所得者の退職金課税は優遇され、過ぎなのか、退職金とは、退職所得の3つの優遇措置、退職所得の優遇措置にも問題はある、退職所得の改正、今後の改正の可能性、累進税率が再びひきあげられることはあるのか、超過累進税率の具体的な適用、かって75%だった最高税率、所得再配分機能を担うべきは累進税率、インフレ下過去最高を記録し続ける税収、増のじょうきょうで財源を主張することに合理性はあるのか、ブラケット・クリープの問題、億単位の所得段階をつくる、抑圧的な率にする必要性あたらしい税率税率表のイメージ、累進税率の改正経緯、資産所得の課税にある特例税率、資産所得の課税は強化すべきなのか、中古マンション価格の高騰問題、検討されるべき改正、復興特別所得税の半分を防衛特別所得税に振り替える、ここまでの振り返り、復興特別所得税とは何か、防衛費増税の方向性、防衛費増税の問題、防衛費増税の基本方針、これまでの改正をみると、所得税制のゆくえ、
感想
103万円の壁はない、本質は物価に合わせた生活費の控除、税金は租税法律主義で決めるべき、税金計算は所得分類別源泉徴収、総合か分離、所得ー税額控除=課税所得、控除と非課税を解説、憲法理念に反する所得制限を取り上げ、退職所得、復興特別所得税の防衛費振替に言及、国民は税制を勉強していく時代を実感、
まとめ
わたしたちの税金はどのようにきめられるのか、所得税はどのように計算されるのか、103万円の壁問題の本質は何か、サラリーマンにも経費の控除がある、所得控除を制限する税制のトレンドは妥当か、大学生の親の扶養控除はどう変わったのか、給与所得者の退職金課税は優遇され過ぎなのか、累進税率が再び引き上げられることはあるのか、復興特別所得税の半分を防衛特別所得税に振替を考察日本の所得税制を解説し、問題点を指摘
せいか