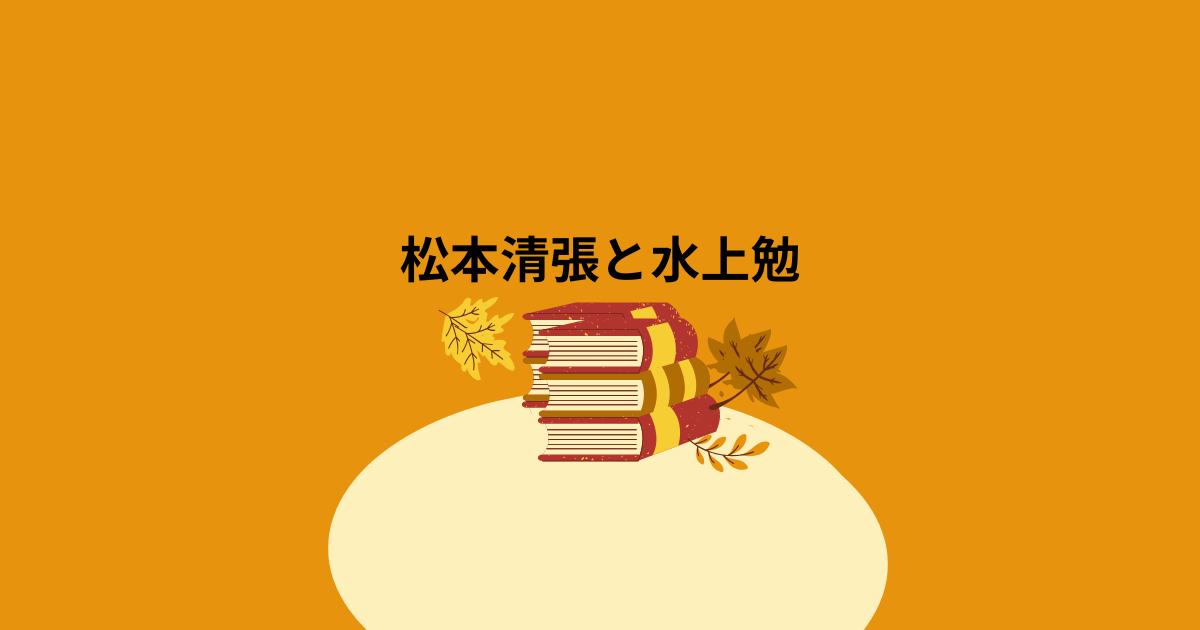実は似た者同士、雑食の果てに―社会派推理小説時代の終焉、様々なジャンルへの飽くなき挑戦―文学・言葉を越えてその軌跡を辿る著者は藤井叔禎、立教大学名誉教授、立教大学大学院博士課程単位取得退学、専門は近現代日本文学・文化、著書「東京文学散歩・を歩く」他
概要
文壇作家時代の松本清張、探偵作家から見た文壇作家、文壇作家時代の清張ー推理小説と現代小説、デビュー作「西郷札」は大衆小説なのか、仕掛けとしての秘密・隠蔽、推理小説への意識の高まり―誤読をきっかけに、明確な推理小説「記憶」ー満載の謎、そして謎とき対決、さまよい続けた文壇作家時代ー多芸は無芸、初期水上勉は私小説家だったか、生活年譜として「フライパンの歌」、私小説の三要素ー分身・体験・場所、意外と少ない「私小説」、「風部落」、「決潰」「枯野の人」、私小説の周りを取り巻く小説群、清張の乱歩批判、乱歩と清張の未完の対決、清張の推理小説論―本格派は児戯である、清張による戦略的な乱歩否定、清張と野心と肯定のノイズ天城越えは伊豆の踊子をどう超えたか、仮想敵としての「伊豆の踊子」。「天城越え」を貫く反「伊豆の踊子」意識、オーバーラップする二つの作品、二人の私と差別意識、差別とは無縁な私の感情、私の人生行路ーアンチ純文学の戦いの果てに、清張の江藤淳批判、ヌーボー・グループと若い日本の会、関川のモデルは江藤淳、文化人への嫌悪感と江藤淳批判、江藤への執拗な論難と三田村鳶魚、揺るがぬ文壇・純文学批判、映画「砂の器」は小説をどう補修したか、小説「砂の器」の構造的欠陥、今西の推理過程ー東北地方へのこだわり、紙吹雪の女、情報不足による今西の推理の遅れ、根拠不足という致命的な綻び、唐突な和賀の浮上への釈明、純文学派への闘争心ゆえの小説の構造的破綻、「点と線」から「日本の黒い霧」へ、一つの起点としての「点と線」、トリック過剰への反省から生まれた「ある小官僚の抹殺」ノンフィクションと小説との分岐点、「小説帝銀事件」における諸問題の改善、小説としてかくつもりだった「日本の黒い霧」、史眼をもった文学への確信、私とはすなわち清張その人である、渦中でもがく人間を描くにはー推理小説的手法の回帰、推理小説家時代の水上勉、清張が依拠した方法論―木村毅「小説研究16講、「霧と影」の分身たち、客観化と濃密な分身の狭間で、」社会的事件への鋭いまなざし、「海の牙」から「飢餓海峡」、アンチ私小説・社会的事件重視の系列の終焉、日本型私小説を極める―その後の水上勉、推理小説から日本型私小説へ、母・そして修行時代、女性たちへの追慕、「寺泊」いろんな時期の・いろんな人間関係の・いろんな人間関係の、いろんな話、様々な試みに投影されるわたくし、第一私小説集としての「雁帰る」、私小説から派生した二つの流れ―ルポルタージュと評伝、主役へと躍り出た評伝の営み、国民的文化人・松本清張ー読書世論調査の結果から、巨大な文化人的存在として、読書世論調査における清張、本の売れ行きとの関係、好きな著者ランキングの推移、なぜ良いと思った本は順位が低いのか、1961年以降の大きな断層、旧作の根強い人気と小説以外の分野への進出、言葉を越えた世界へ・水上勉ー「才市」の奇跡、才市の生き方への強い共感、ハンディと輝きとの逆説的な関係ー才市型人間の捉え直し、父母を通じて才市に流れ込むわたし、カンナ屑と父の思い出、「電脳暮らし」そして慧能への深いまなざし、言葉を越えた世界―沈黙が語りかけるもの、詩よりも従容たる実践ー俗世の無言詩人として、
感想
似た者同士、様々な職業を経験、推移小説作家から社会派小説家に転身していった文学的生涯を辿る、清張・水上の第三弾評伝、
まとめ
文壇作家時代の松本清張、初期水上勉は私小説家だった、清張の乱歩批判、天城越えは伊豆の踊子をどう超えたか、清張の江藤淳批判映画「砂の器」は小説をどう補修したか、「点と線」から「日本の黒い霧」へ、推理小説家時代の水上勉、日本型私小説を極める―その後の水上勉、国民的文化人・松本清張ー読書世論調査の結果から、言葉を越え世界へ・水上勉ー才市」の奇跡を考察、二人の推理小説作家から社会派小説家へ転身した生涯を描く。