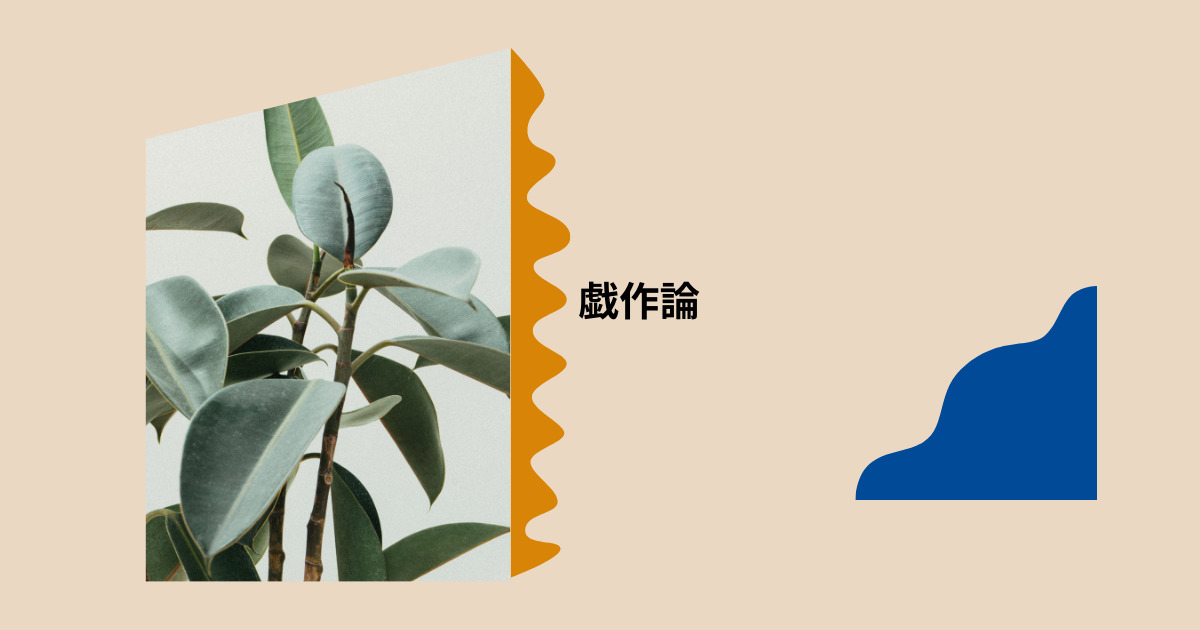戯作のどこが、現代人の批評眼にそぐわないないのか、周作人は滑稽本を日本人自身が創作したあそびだと評している、戯作には古典文学の残滓が沈殿、著者は中村幸彦、近世文学研究者、京都帝国大学文学部国文科卒業天理図書館司書を経て関西大学教授、著書「宗因独今・俳諧百韻評釈」他、1998年没、
概要
戯作の意義、体系的概念と歴史的概念、国文学者の使用例、戯作・創作についての社会の意識、歴史的概念・戯作、戯作の範囲、戯作の用例(漢詩文・和文・宝暦明和期・安永天明以後)、戯作の範囲、戯作即ち当世本、戯作の意義と読み方・語源、戯作の発生とその精神1、戯作発生期の時代外観、文化界の様相、養子論議、文人趣味、文人意識、文人趣味の流布、戯作の発生とその精神2,強い自己意識、知識人の処世態度、即世的姿勢、慨世的姿勢、離世的姿勢離世的精神、千葉芸閣の場合、武田梅竜の場合、老荘思想の流行、第二文芸に遊ぶ、当代の文学思潮1,雅俗の論、前期戯作界、当代の文学思潮2-雅俗のくるい、俗への傾斜、文学的放蕩、中国の洗例、知識人の小説界進出、新風体の創出、使用した戯作の意味、自給自足的戯作界、例の1-跖婦伝、2-沢田東江、後期戯作界、寛政の治、戯作者の交替、新しい読者層、後期戯作者の態度、出版界の様相、文学界の全国的統一の気運、三都書物屋仲間の関係、小説出版の形態、作品の大衆性、作品の商品化、職業的・準職業的戯作者、戯作者気質、卑下慢、職人性、戯作表現の特色1,一うがち穴、うがつ癖、気質、息過、高慢・自慢・みそ、江師、病・失・非、うがちの姿勢、悪口、風刺・教訓、裏面観・側面観、うがちの性格、無用・むだ、徘徊趣味、ニちゃかし、用語例、表裏の二面、黄表紙の絵、論議体洒落本の例、のぞき、三馬作品の例、はぐらかし、社交性、呼吸、戯作表現の特色2,趣向、世界と趣向、趣向をめぐる作者と鑑賞者、趣向の性質1・遠心力性、2・新奇、3・非第一犠牲、4・読者の協力の予想、5・構図性、趣向の性質の概要、文壇の原因、文学の芸能的性格、戯作表現の特色3,見立、へんちき論、吹寄、綯い交、地口、戯作における出現の様相、戯作以外における見立、戯作文章の特色、客観的描写、感覚的描写、二面描写、狂講的舌耕、舌耕的文章の特色、戯作の文章の変化、黙約の文章、末梢的描写、構成的文章、戯作作風の推移、草双紙界、洒落本から人情本へ、滑稽本の前後期の相違、作風変遷の大勢、読本の前後期の相違、小説の位置の上昇、
感想
戯作は江戸時代に、文人趣味の流布、離世的精神を以て成立、前期と後期にわけ戯作界を解説、戯作表現の発想法・構成・趣向・文章・作風について特色を述べた戯作論、
まとめ
戯作の意義、戯作の発生とその精神、前期戯作界、後期戯作界、戯作表現の特色、戯作文章の特色、戯作作風の推移を考察、戯作の現代における冷遇とはいかなるものかを考える、