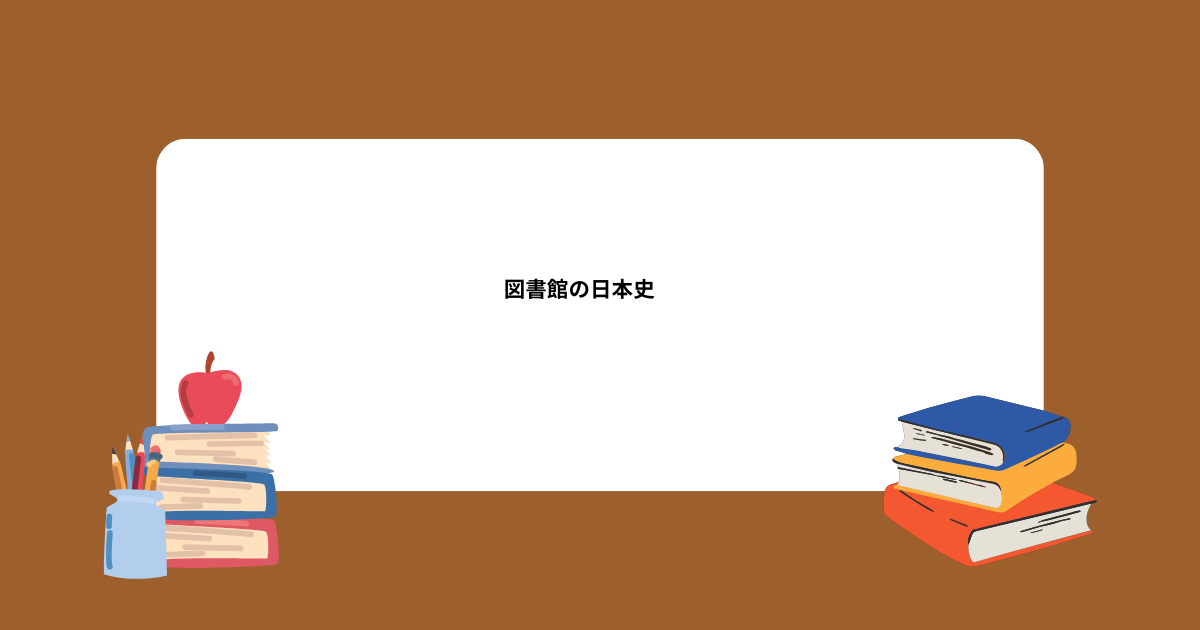図書館は情報を介して人と人とを結びつけるコミュニティゾーン、日本の図書館史を辿る、著者は新藤透、筑波大学大学院図書館情報メディア研究科博士後期課程修了、國學院大學文学部教授、著書「松前影広・新羅之記録・の史料的研究」他
概要
古代の図書館、図書の誕生と図書館の起源、語り部、結縄、文字、2飛鳥時代の図書館、大化の改新と律令、奈良時代の図書館、図書寮、経蔵・写経所、蔵書家、平安時代の図書館、紅梅殿、江家文庫漢籍蒐集、「玉葉」、中世の図書館、1鎌倉時代の図書館、寺院文庫、武家文庫、金沢文庫、2南北朝・室町・戦国の図書館、足利学校、戦国大名の書籍蒐集、山口殿中文庫、静勝軒文庫、「言国卿記」書籍蒐集に励んだ皇族、天正遣欧使節団、近世の図書館、将軍の図書館、駿河・富士見亭文庫、紅葉山文庫、大名の図書館、尊経閣、明倫堂、3国学者の図書館、荷田春満、本居宣長、神社文庫、4庶民の図書館と情報ネットワーク、貸本屋の隆盛、羽田八幡宮文庫、青柳文庫、野中家、石黒家、近代の図書館、1明治の図書館、町田久成、市川清流、文部省博物局書籍館、東京書籍館、帝国図書館、集書院、公立図書館設置運動、通俗図書館・千野図書館、佐野友三郎、集古会、大正の図書館、東京市立図書館、日本図書館協会、昭和戦前期の図書館、図書館令改正、中央図書館制、読書会、昭和戦後期の図書館、CIE図書館,米国教育使節団、図書館法、コミュニティとしての図書館の復活、官主導と民間、マイクロライブラリーと新しいコミュニティの場,
感想
古代から近代にかけての図書館の利用実態や情報・コミュニケーションの観点からまとめた通史、図書館とは情報交換・コミュニティ形成の場である、
まとめ
古代の図書館、飛鳥時代の図書館、奈良時代の図書館、平安時代の図書館、中世の図書館、近世の図書館、近代の図書館を考察、コミュニティとしての図書館の復活を語る、