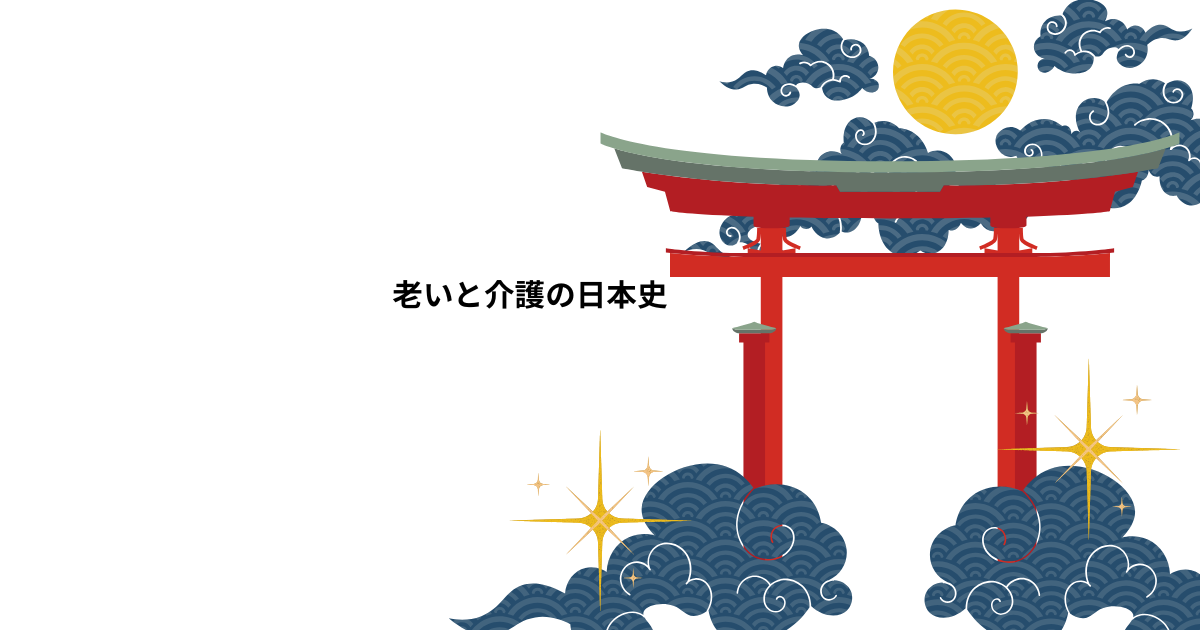日本社会において、老化に随伴する老病と老耄がいかに認識され、患う老人が人々からどう見られ、どのように介護された来たのかを通史的ににたもの、著者は新村拓、早稲田大学大学院文学研究科博士課程修了、北里大学名誉教授、著書「日本医療史」他
概要
嫌われる老いと讃えられる老い、嫌われた老人の生理、古代と現代の認知症診断基準、長寿を祝う心と老苦を恐れる心、厄年を忌む心、寂しさの募る不老長寿、病苦を厭う心と死を恐れる煩悩、蔑まれた老醜と讃えられた老いの知、謡曲「卒塔婆小町」に見る老い、景清と花鏡、竹馬抄、貝原益軒、西鶴と宗室、老人を支える養生法と医療、学者たちの説く老人論と医療、老人医療と養生法、長寿もほどほどに、老いをいかに迎えるか、益軒の五計、人生五十年、心構え、老耄は運命、老人の健康を支える技と知識、老人の食事・衣服、未病を治す、医薬知識、近世における老耄介護の実践、老人介護の手本、近世の老老介護、家計の窮地を招いた介護、老化に伴う行動面の諸症状、過食、介護のための工夫、介抱、伝統的な看取りの作法、老いと病と死、死と信仰、近世の医師と薬、老病と延命治療、自殺、近世における看取り、臨終の作法、死後の措置、「往生要集」、法州が説く臨終看病法、「家内用心集」、近現代の老人、西洋医学の導入と囲い込まれる精神障害者、痴呆、「精神病約説」と癲狂院「老耄狂」、近現代老人介護の担い手、厭がらせの年齢、楽隠居への批判、別居か同居か、女中の雇用、寝たきり老人、養老院、戦後の福祉制度の展開、老人問題、同居と別居、社会的入院、日本型福祉社会、認知症老人対応、介護保険法、超々高齢社会、長教員瀬教員、
感想
認知症への眼差し、老いと介護の日本史、嫌われた老いと讃えられた老があり、養生法と医療、伝統的看取りがあったが、西洋医学導入で精神障害者とされ、家族崩壊から介護の社会化に注目、人生50年から高齢者社会となった日本介護史、
まとめ
嫌われる老いと讃えられる老い、老人を支える養生法と医療、伝統的な看取りの作法、近現代の老人を考察、昔から嫌われた認知症とその対応(養生法と医療、伝統的な看取り)、西洋医学導入で高齢者社会となった今、介護の社会化について考える、