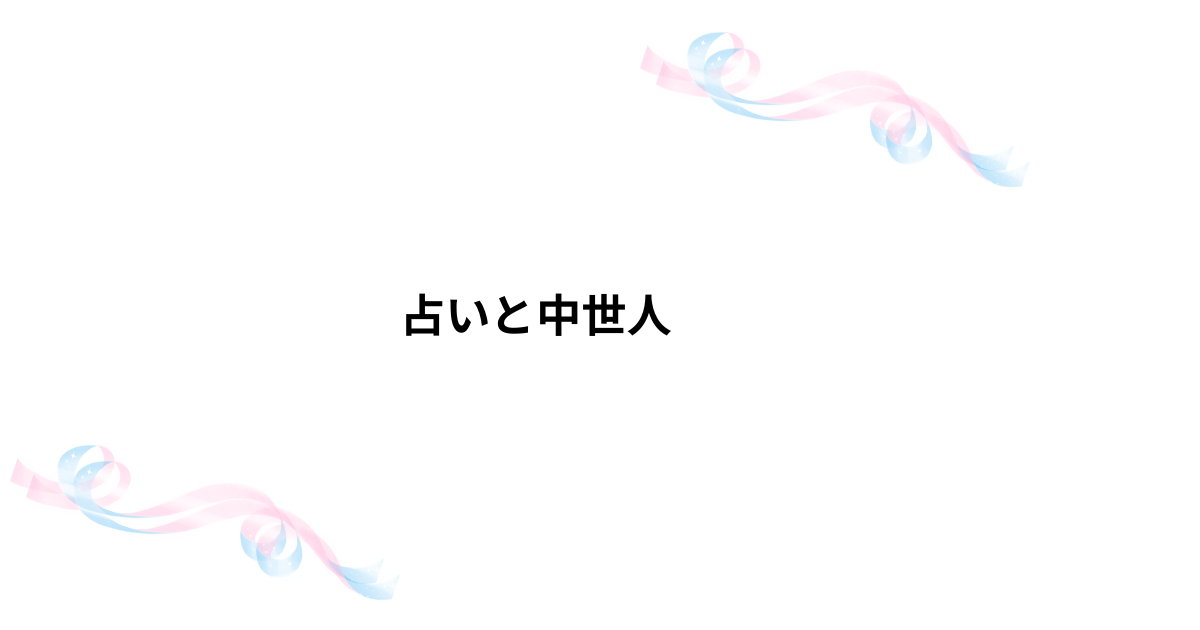占いは中世の日本人にとって、生活や政治にとって欠かせきょうないものであった、当時の日記や古文書から明らかにする、著者は菅原正子早稲田大学大学院文学研究科博士後期課程単位取得退学、学習院女子大学非常勤講師、著書「中世公家の経済と文化」他
生活の中の占い、妻のゆくえは、山科教言の場合、日に血を決める、事件の解決、祓と暦、朝廷の占い、幕府の占い、1宮中の占師たち、神祇官の卜部、亀卜、内容は幅広い、2天皇と御卜、祟りがあると出た場合、軒廓の御卜、卜文、蔵人所の御占、3鎌倉の怪異、三人の陰陽師、承久の乱と占い、動物と昆虫、宿曜師珍誉、実朝の夢、陰陽道の鬼気祭・夢祭、陰陽師の家、1安倍晴明の実像、生まれは讃岐国、大器晩成、陰陽の達者、六壬式占と占事略決、藤原道長、2足利義満が好んだ陰陽道祭、安部泰親の活躍、安部氏と賀茂氏、足利義満と陰陽道祭、泰山府君に祈る都状、義満の死、将軍の夢を占って、義教の機嫌損ねる、土御門と勘解由小路家、3若狭国名田荘上村、紀伊國と近江国の祈禱料所、若狭国名田荘と土御門家墓所、有春・有脩父子の在国、公家の地方在僧侶による国、収入源は守護武田氏、諸口雑務寮、天変地位と政治、1日月と惑星の変異、「合」さまよう惑星、黄道の28宿、羅睺・計都星、2天文密奏、日食と君主の政治、天文占い、3彗星・客星と徳じゅがくと政、天変、平経高の意見、永仁の徳政令、儒学と易占い、1足利学校、将軍の運勢を占う、創設をめぐる諸説、公方足利利持氏の野望、永享の乱と上杉憲実、2講義の内容、学規三ヶ条、古注と新注、3庠主による占筮伝授、第一世庠主快元、九華、僧侶にによる学問教育、綿谷周瓞易経、占筮の伝授、豊臣秀次に仕えた三要、家康への講義、戦国の世と占い、1武田信玄と占い、四聖人像と易占い、越後勢との戦いを占う、易経を学んだ信玄、伊豆への出兵を占う、儒学と分国法、喧嘩両成敗法、山本勘助、2鬮に神意を問うー島津氏、明から帰化した友賢、土井覚兼、心易で占う、鬮、南蛮犬と羽柴秀長、3算木を置く公家―山喧嘩両成敗法、狂言「居杭」の算置算卜占い、龍天院覚弁、山科言経と算木占い、
感想
中世は占いなしでは暮らしていくことができなかった、様々な占いがあり、政治・学問・合戦に欠かせないものだった、陰陽師や僧侶が活躍した中世社会の実態に迫る、
まとめ
生活の中の占い、朝廷の占い・幕府の占い、陰陽師の家、天変地異と政治、儒学と易占い、戦国の世と占いを考察、占いなしでは暮らしていけない中世の人々の実態に迫る、