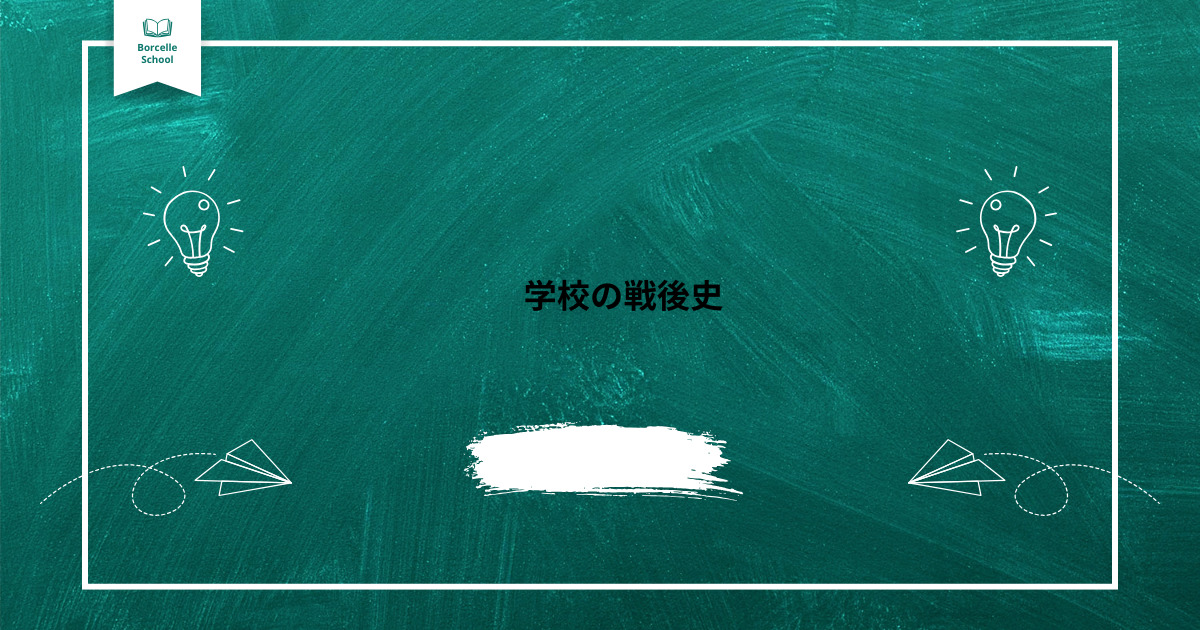旧版「学校の100年史」を改定、コロナ過・団塊の世代が後期高齢者・ウクライナ侵攻・中東紛争を受け戦後が自明の理とは言えなくなった、戦後の学校を新たな視点で描く、著者は木村元、東京大学大学院教育学研究科博士課程単位取得退学、専攻は教育学、青山学院大学コニュニティー人間科学部特任教授、著書「人口と教育の動態史」他、
概要
就学・進学動向からみる戦後ー学校の受容と定着、就職動向からみた学校の定着、戦後の学校の課題の変遷、日本の学校の成立―近代学校の導入と展開、1産業革命と近代学校、原型としての工場方式、2日本の近代学校、小学校の形成、3生きられる場の形成と葛藤、教員文化の形成、新学制の出発―戦後から高度成長期、1戦後の学校の枠組み、教育基本法と六三三制、2教育行政とカリキュラム、学習指導要領に基づくカリキュラム、3戦後初期の学校の動静、山びこ学校、学校化社会の成立と展開ー経済成長下の学校、1高度成長と学校、学校システムの均質化、2出口の展開―中学校の変化、高校への通過点、3高校の大衆化、ベビーブームと高校全入学校間接続問題の諸相―中学校と高校の接続、入試改革・5段階総体評価・内申書、5産業化社会への対応への諸相、系統学習と道徳6学校への異議申し立て、反乱の展開、学校の基盤の動揺ーポスト経済成長に四半世紀、1制度基盤の変容、目標・評価システムの導入、2学力と学校制度の新動向、ゆとり教育と新しい能力、3自明性の問い直し、学級崩壊、4キャリア教育と公共性の教育、5土台を支える取り組み、居場所としての学校、問われる公教育の役割ーこの10年の動向を軸に、1学校の見直しの動向、六三制の変容、2学校制度の周辺・周縁の活性化、夜間中学・通信高校・適応指導教室・外国人学校、3公教育の境界の拡大・融解、公教育と民間教育事業、4デジタル化のインパクト―オンラインの導入、5人口減少社会の地域と学校、離島・中山間地域高校の取り組み、6教育のグローバル化と学校、国民教育の問い直し、7教育課程編成への反映、高校普通科の再編とカリキュラム改革、8教えることの岐路、主体化への働きかけ、学校の世紀を経て、1学校の世紀としての20世紀、2学校に行くことへの多義性、3学校の役割再考、学校の戦後史を描く、
感想
団塊の世代が後期高齢者となった、学級文化を軸とした日本の学校は揺らいでいる、多様な学習場所、選択を価値とする学校制度改革同質性の強調と競争の教育の払拭が必要に共感、
まとめ
日本の学校の成立、新学制の出発、学校化社会の成立と展開、学校の基盤の動揺、問われる公教育の役割、学校の世紀を経てを考察、学級を軸とした学校の戦後史を描き、問題点を指摘、